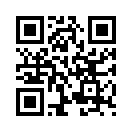2008年08月30日
イースト菌
「ママでも金」は谷様。
パパ達は菌、イースト菌。
男のパン教室に行ってきました。
土曜日、朝10時、中央公民館。
一番乗り。
頭にバンダナ、腰にはエプロン。
液体石鹸ミューズで手を洗い、準備OK。
今回はマヨネーズパン・ウインナーロールを作ります。
実は輝さん、初体験です。
包丁屋さんが料理の一つも出来んでどなんすんねん。
やったろうじゃねえか。まずはパンからね。
今回は事前準備はすべて先生が遣っておいてくれました。

当然二時間近い作業Dすので、奥が深いのでありますが、何はともあれ焼き上がりました。

各自のお皿に盛り付け。

アイスコーヒーと共に、いただきました。
我は一個だけ食べて、家で今か今かと待ちわびる一人娘にお土産です。
でも楽しかった、面白かった、美味しかったです。
またやりたいです。
今度は赤ワインに合うフランスパンに挑戦したいな。
アンxxセンに負けないように頑張ろう。
餡出る栓にならないように。
パパ達は菌、イースト菌。
男のパン教室に行ってきました。
土曜日、朝10時、中央公民館。
一番乗り。
頭にバンダナ、腰にはエプロン。
液体石鹸ミューズで手を洗い、準備OK。
今回はマヨネーズパン・ウインナーロールを作ります。
実は輝さん、初体験です。
包丁屋さんが料理の一つも出来んでどなんすんねん。
やったろうじゃねえか。まずはパンからね。
今回は事前準備はすべて先生が遣っておいてくれました。

当然二時間近い作業Dすので、奥が深いのでありますが、何はともあれ焼き上がりました。

各自のお皿に盛り付け。

アイスコーヒーと共に、いただきました。
我は一個だけ食べて、家で今か今かと待ちわびる一人娘にお土産です。
でも楽しかった、面白かった、美味しかったです。
またやりたいです。
今度は赤ワインに合うフランスパンに挑戦したいな。
アンxxセンに負けないように頑張ろう。
餡出る栓にならないように。
Posted by 輝 at
19:22
│Comments(3)
2008年08月29日
赤坂で会議

極力、朝早い会議が好きです。
もともと朝派ですね。
今日は赤坂で会議。
終了は11:30でした。
昼飯でも行きましょう。
この一声で、レッツGO。
何となく、魚がいいなあ。
松花堂弁当、鯖の竜田揚げがメイン。
それに鳥唐揚げ、シュウマイ、などなど。
なんと630円。
これは特許物です。(少し無理やりですが)
場所は特許庁、地下の食堂。
身分証明書が必要ですが、免許証でOK。
美味いよ。
Posted by 輝 at
18:54
│Comments(1)
2008年08月29日
居合稽古

昨夜は中央公民館で蕨そうけん会、居合の稽古でした。
いよいよ5本目に突入。
門下生の仲間で話すのですが、良くぞ一年半続いたと。
自分もX日坊主の典型なので、驚いています。
もっとも稽古のお陰で、お客様から刀剣選びのアドバイスが
良くなったよとお褒めの言葉も。
やっぱ現場知らなきゃ、話になんめえ。
と思う、ネットショップ店番なのです。
Posted by 輝 at
06:35
│Comments(1)
2008年08月27日
千両箱

そうだ、千両箱作ろう。
ドル箱?
それはパチンコ屋さんにある箱。
大当たりの人が玉を入れる箱です。
現在は樹脂製ですが、昔むかしは木製でした。
クギでしっかりと止められて送られてきます。
叔父が遊技場を経営していたので良く手伝いました。
裏方さんは主に東北からの出稼ぎの方や、いわくありげの夫婦?者ですが、皆、良い人です。
また、昔を思い出しました。
話は千両箱でしたね。
鼠小僧が担いで逃げたと言われる千両箱?かい。
そんなもん、ねえよ。
じゃ探してよ。
通信販売会社のバイヤーさんとの会話です。
こういう時に役立つ会社が、本当に良い取引先ですぜ。
お忘れなくね。
てな訳で、出来ました。
歴史のお勉強、日銀さん見学などなど時間が掛かりましたので、ブログも長いです。
ご容赦。
夢も一緒にまとめて入れれば値、千両。
<<千両箱とは>>
江戸時代の金銀貨幣保管容器の一種です。
金貨幣収納の物を「きんばこ」、銀貨幣収納の物を「ぎんばこ」
この様な表現が正しいと考えられます。
しかし金貨幣の場合は、小判千両(千枚)収納が通例の事から、何時とはなく、
「千両箱」と呼ばれる様になり、一箱と言えば金千両の事となりました。
当時の金貨幣は大判、小判、ニ分金、一分金等ですので、それぞれ千両の容積は異なり
千両箱の大きさは異なっていたと思われます。
当然大きさはまちまちで一万両収納の超大型の物も作られた
と考えられますが、人間一人か二人で扱うべき物であるから
中味含めて20キロから40キロの範囲が限度であろうと考えます。
材質は松、欅などの木製で周辺、中央に鉄製枠、帯金を付けた物が多く、全て鍵を施してあります。
上板の半分を開け閉めする形が多く、上板には家紋、屋号を書いた物が多い。
いわゆる金庫にあたるが、小銭専用の銭箱の丁銀箱に比べるとその作りは堅牢であった。
ちなみに丁銀箱とは、おおだなの店先で、丁稚小僧(俺の事)が客から頂戴した小粒銭を
するりと放り込む箱。
店が仕舞うと、番頭さんが奥でウヒウヒ言いながら銭勘定している大だんなさんのもとに
運ぶんでやんす。
あれです。
新撰組のドラマ?の時かな。
NHK渋谷放送センターで見ました。
<<桐の千両箱>>
古文書や歴史書からやや現代風にアレンジした千両箱を考案した。
大切な宝物を保管したり、インテリアとしての価値もあればと材料には桐材を使い
仕上げも時代仕上げ(板焼き仕上げ)を施した。
実用面(火事などから簡易的に守る安全面も考慮)からも板厚は2.2cmにする等も工夫もされている。
要所金具は鍛冶師に頼み、特別に誂てある。
飾り金具、太鼓鋲など工夫がなされている。

又上板開閉部分には蝶番を使わず、差込仕上げとしてある。
摩擦消耗面が無いので、これも長持ちさせる工夫である。

製作者の山田 章さん大好きです。
カラオケ上手い、伝統工芸師です。
<<桐の千両箱製作者>>
1)山田章師経歴
2004年7月現在
7代目山田桐箪笥製作所代表
伝統工芸士(認定番号1494)
春日部桐箪笥工業協同組合副理事長
昭和12年5月28日生れ
職歴48年
昭和31高等学校卒業後
父、山田敬治師(伝統工芸師)に師事
後、東京で名高い、川崎正夫師に指示本格製作修行に入る
昭和53年春日部桐箪笥工業協同組合の副理事長となる
昭和55年伝統工芸師に認定される
<受賞歴>
昭和55年
・埼玉県主催伝統的手工芸品コンクール
伝統的工芸品産業振興協会会長賞受賞
・昭和59年東京通商産業局長(現経済産業省)より
伝統工芸師、産地功労者として表彰される
2)新作品へのこだわりDNA
師の作品へのこだわりDNAは父、敬治師はもとよりでは
あるが、初代山田長松師にまで遡る必要があろう。
探求心と進取の気性にとみ、製作までに掛ける研究時間
は並大抵ではない。
得心行くまで文献をあさり、ヒントを見つける。
今回作品「千両箱」も形状、材質吟味、金具の全てに
渡り、納得行くまで、捜し求めてきた。
材料の厚みへのこだわりは、中に仕舞う物への配慮である。
万が一火事などで火が近づいても十分耐えうるように2.2cm厚の材料を使用した。
3)桐の特性・取扱い
柔らかな桐の加工には何と言っても使う刃物が切れなくては話しにならない。
その刃物の手入れも並大抵ではない。
又、桐は何年たっても生き物、伸び縮みする。
桐の気性を経験で知る事も大切だ。
桐の特徴は数多くあるが代表的には
・断熱性に優れている
熱伝導度が小さく、炎にあたった場合も表面が炭化した後は熱気を通しにくく
なり、内部を火から保護する性能が大きい。
金庫の内箱などに使用されるのもこの特性の為です。
・防虫効果に優れている
衣類・掛け軸・刀剣類等の収納に最適な素材として使用されています。
4)歴史書に見る春日部(粕壁)の歴史
天保13年に近隣の神社に春日部の職人が寄進した際の記録がある。
初代、山田長松始め、数多くの職人、職歴の名前を見ている内に、
刀剣製作などと同じく、桐の製品も分業の文化であると推測される。
1982年執筆された小泉和子氏の「物と人間の文化史」箪笥(たんす)には
当時の職人及びその人数が記載されている。
大工、指物屋、箱屋、木挽などなどである。
材料は全て無駄にはされず、木屑までもが、岩槻の人形の顔製作に使われた
そうである。
良き時代を彷彿とさせる。
同じく埼玉の川越(小江戸と言われる)も同様に、刃物などの製作者が多く
個々の地名にもその名を残す。(例えば鍛冶町)
思うに、水路(舟での物流)の発達と共に、このような文化が栄えたのであろう。
川は物も、文化も運んで来る訳である。
又、作品もその心意気も運び出すのである。
5)過去作品
多くの作品があるが、
箪笥製作の商売はその全てが家具問屋との商いであると言っても過言ではない。
あえて作品の落ち付き所は伏せるが
・歌舞伎名跡の衣装箪笥
・着物の大店に納めた、大名籠
・近隣神社の獅子頭箪笥
などなど名品が数多くある。
残念ながら鍵だけは、現代物(ブルドッグ)です。
キーポイントとはまさにこの事。

材質:桐(中国産)
外形:縦:24.2cm、横:39.4、奥行:14.5cm
内径:縦:20cm、横:35cm、奥行:10.5cm
木厚:2.2cm
です。
札束で6,000万円入ります。(お金持ちが試しました。私ではございません、念のため)
PS:
徳蔵の商売、刀を納める箪笥、刀箪笥もございます。
改めてご紹介します。
★メールでのお問い合わせは★
お気軽にこちらへ
★電話でのお問い合わせ★
TEL(048)431-6600
Posted by 輝 at
17:10
│Comments(2)
2008年08月26日
コフの爪切り:ご縁ができて(1)
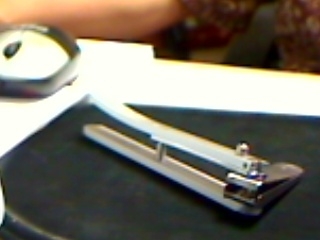
メーカーさんの手伝いで、たまに展示会のお手伝い。
小坂刃物の社長さんとは、東京ギフトショーでお目にかかりました。
まったく?商売っけがない方で、輝さん店番頼むよとふらりと出かけてしまいます。
でも能ある鷹はなんとやら。
すんごい発明家でしたね。
今後も少しづつ紹介します。
店番してて、夕方までに30個売りました。
お客様の声が身近に聞けるチャンスなんてめったにねえと、
奮起しました。

小坂さん、売り上げのXX%も下さいました。
丁重にお断りしましたが、お陰様で、当社を代理店の一つに指定
して下さいました。
これが「コフの爪きり」。

ネツトで見たら、福祉用具の一つにも取り上げられてました。
我がお聞きしたお客様の中で、妊婦さん、介護担当さん、ちょいお腹が出ている方
の爪きりに好評とは実感しました。
爪きりの先がくるりくるりと回ります。
柄もこれだけ長いんです。
使いやすさは判りますよね。
今後も
コフの缶きり、セントルなんて、愉快な商品も紹介しちゃいますから。
画像が上手く出来なくてごめんなさい。
お値段はちびっと高めですが2,625円。
偽者も出るくらいの優れもの。
それにつけても縁とはいなもの、味なもの。
★メールでのお問い合わせは★
お気軽にこちらへ
★電話でのお問い合わせ★
TEL(048)431-6600
Posted by 輝 at
13:33
│Comments(2)
2008年08月25日
すでにOBですが

10年前に設立に参加しました。
SOHO(ソーホー)と言います。
スモールオフィス(SO)
ホームオフィス(HO)
の略称です。
一時期ほどは騒がれなくなりましたが、
いまだに仲間内での活動は継続中。
月例会では結構専門的な話題で盛り上がります。
先週は浦和で、暑気払い、気合の入るビジネスモードでした。
バーチャルですが、ビルを建てました。
この利用方法も勉強の一つです。
SOHOネットワーク埼玉ビル
ビル入り口はこちらです
TOPページの屋上のヘリが離陸、やがてコンコルドが
フランスに向けて旅立ちます。
当社の居合刀もコンコルドで運びます。(笑い)
各フォロア毎に楽しいコンテンツが入っております。
ビル10F
動画でのメンバー紹介も見てください。
7F
kiritori、困った時にはここを見てね。
解決策盛りだくさん。
ビル6Fは当社も入居しています。
ウエブショップ紹介です。
<<お知らせです>>
9月も月例会を開催致します。
オブザーバー参加歓迎です。
参加費は会場負担金200円のみです。
Posted by 輝 at
09:00
│Comments(3)
2008年08月23日
三学院、地蔵尊供養

明日(8月24日)夕方(17時から21時)、蕨、三学院さんで地蔵尊供養が開かれます。
19時からは護摩供養も行われます。
合わせて、17時より縁日がたち、納涼ビヤガーデン、夜店も出ますよ。
今年は幸いなことに、日曜日とずばり重なりました。
縁起が良いね。
やはり子供の頃を思い出します。
故郷、三島にも愛称を「おにっちょさん」と呼ばれるお地蔵さんがあり、
地蔵盆がたちました。
郷愁を感じます。
秋の気配も漂うこの頃、是非お越しください。
お子様はもちろん、ご家族全員でのコミュニケーションにもなります。
<<以下はウィキペディアの掲載記事より引用させていただきました>>
地蔵盆(じぞうぼん)は、地蔵菩薩の縁日である8月24日に向け、その前日の宵縁日
を中心とした3日間の期間を指し、またそのうちの日を選んで行われる地蔵菩薩の祭
のことを言う。
ただし、地蔵盆は寺の中に祀られている地蔵菩薩を対象とはしていない。道祖神信仰
と結びついた路傍あるいは街角(辻)の地蔵が対象となっているのである。
地蔵盆の提灯元は地蔵会(じぞうえ)、地蔵祭と呼ばれたが、8月24日が裏盆にあた
ることから、盂蘭盆にちなんで地蔵盆と呼ばれるようになったと言われている。
現代では、参加する人々の仕事などに合わせ、多少日程をずらして土日に行うところも増
えている。
Posted by 輝 at
07:11
│Comments(2)
2008年08月22日
亀帰る

数日前に、友人の愛亀が脱走しました。
名前は「花ちゃん」。
何でも良く判る、可愛い子です。
友人は早朝の武道稽古中にマンション庭で散歩させていたそうです。
しかし、驚くほど亀の足は速いのです。
「うさぎ」より早いのは周知の事実。
探した時にはすでに、どこか?(もしかして竜宮)にお出かけしてました。
途方に暮れる家族、特に奥様は、旦那さんよりも大切な(失礼)亀様でやんす。
我も微力ながら、毎朝マンション上階から廻りを見まわしておりました。
それがそれが、今朝、工事現場の責任者さんが、バケツに入れた亀を届けて
くれたので。
まさしく「花ちゃん」。
この首の伸び具合、亀甲模様、間違えない。
数日ぶりのご対面。
感激の瞬間です。
実は、マンションの管理人さん(近年はフロントマネージャーさんと言いますから)
も毎朝、庭には何時もより多くの水をまき、万が一に備えていたのであります。
顛末は工事現場に迷い込み、それを見つけた若いお兄さんに拾われ、自宅で
数日間飼われていたのだそうです。
それも手厚い手厚い待遇で。
心を決め、電信柱の貼り紙を見て、お届け下さいました。
でもこのお兄さん、別れが辛かったそうです。
たかが亀、されど亀。
「花」はきっと長生きするでしょうね。
ギネス更新?
亀は百万年。
でも良かった良かった。
飼い主のお父さんは、二度と亀には散歩させないと心に刻んだ夏のお話でした。
やっぱりこのお父さん、白髪が増えてました。(浦島)
Posted by 輝 at
08:48
│Comments(1)
2008年08月20日
良い日でした
市内には友達の紹介で、包丁を買って下さる方がおります。
ありがたいですね。
店を市内に持っていないので、たまには市内を歩いてお顔を見ると
一声掛けます。
包丁の具合は如何ですか?
今朝も市内の画材やさんでご挨拶。
先日お買い上げの文化包丁、具合は?
切れすぎて怖い位とお褒め?の言葉。
しばらく立ち話。
ねえ、お宅の包丁じゃないけど砥いでくれる?
もちろん、喜んで。
数が多いときは、武生の伝統工芸師さんにお願いして砥いで
貰いますが、今回のような場合には、徳蔵さんの出番です。
包丁は日本橋の老舗のお品です。
余談ですが、良い包丁は、機械砥ぎには出来るだけ出さないほうが良いですよ。
グラインダーの熱で、焼きが戻りますから。
当社では居合刀も同じですが、他社品も喜んで、修理・砥ぎなども受けます。
ですが、一度当社で手を入れた商品は、今後は当社の責任範囲です。
そこは肝に命じています。
帰り偽は果物用にペティナイフのご注文もいただきました。
ありがたいことです。
当社は刃物屋(兼業ですが)。
徳蔵さんは鰹節も鉋で削り、削りたてを毎朝食べてます。
思い立って、市内の商店に出向きました。
ここでは以前に蕎麦汁(創味と言う名前)を買った事があり、
あまりにも美味しかったので寄って見ました。
ありましたね、薩摩の本節が。

少し大ぶりを購入。
きっと徳蔵さん喜ぶだろうな。
汗をかきながら行ったので、帰りに乾物店の女将さんが冷えひえのお茶を
下さいました。
こう言う心遣いも、嬉しいですよね。
商店街ならではのサービスです。
ありがたいですね。
店を市内に持っていないので、たまには市内を歩いてお顔を見ると
一声掛けます。
包丁の具合は如何ですか?
今朝も市内の画材やさんでご挨拶。
先日お買い上げの文化包丁、具合は?
切れすぎて怖い位とお褒め?の言葉。
しばらく立ち話。
ねえ、お宅の包丁じゃないけど砥いでくれる?
もちろん、喜んで。
数が多いときは、武生の伝統工芸師さんにお願いして砥いで
貰いますが、今回のような場合には、徳蔵さんの出番です。
包丁は日本橋の老舗のお品です。
余談ですが、良い包丁は、機械砥ぎには出来るだけ出さないほうが良いですよ。
グラインダーの熱で、焼きが戻りますから。
当社では居合刀も同じですが、他社品も喜んで、修理・砥ぎなども受けます。
ですが、一度当社で手を入れた商品は、今後は当社の責任範囲です。
そこは肝に命じています。
帰り偽は果物用にペティナイフのご注文もいただきました。
ありがたいことです。
当社は刃物屋(兼業ですが)。
徳蔵さんは鰹節も鉋で削り、削りたてを毎朝食べてます。
思い立って、市内の商店に出向きました。
ここでは以前に蕎麦汁(創味と言う名前)を買った事があり、
あまりにも美味しかったので寄って見ました。
ありましたね、薩摩の本節が。

少し大ぶりを購入。
きっと徳蔵さん喜ぶだろうな。
汗をかきながら行ったので、帰りに乾物店の女将さんが冷えひえのお茶を
下さいました。
こう言う心遣いも、嬉しいですよね。
商店街ならではのサービスです。
Posted by 輝 at
16:14
│Comments(2)
2008年08月19日
片付け作業中
久々に事務所の整理。
決算作業でばたばたしてました。
少しは綺麗にしないと思い、片付け開始。
なのですが、なぜか昔買ったが読みかけの本を発見。
ビジネス本はIT関係でなければ、少々古くても役に立つ。
「エスキモーに氷を売る」
「なぜ、あの商品は急に売れ出したか」
は何度読み返しても、刺激を受けます。
当然、片付けは進みません。
なぜこんな本をとっておいたか?
「ひとり暮らし 料理の技術」
津村 喬 著
1977年の本ですから、約31年前購入です。
まだうら若き、IVYBOYでした。(笑い)
この中に、料理道具に関する記載があります。
当時はまだコンピューター会社でSE修行中でしたから
まさか、包丁製造販売の仕事をするとは、考えてもみませんですね。
その包丁に関する記載を読んで、おもわずにんまり。
料理の半分は切ることにある。
とりあえず買いたいものは、万能包丁、砥石とありました。
包丁だけは良いものを買いたい。
切れない包丁は材料を切らずに、つぶすことになる。
等と記載されてました。
良いこと書くね、一人よがりです。
そんな訳で、徳蔵のペテイナイフ。

最近は小ぶりの食材が多いので、多分、最初はこれ一本でOKかも。
ダマスカス鋼で錆びにくい。(錆びないと書きたいくらい)
それに柄もしっかり出来てます。

マホガニー合板で、いかしてます。
★メールでのお問い合わせは★
お気軽にこちらへ
★電話でのお問い合わせ★
TEL(048)431-6600
★徳蔵ウエブは★
製品情報満載
決算作業でばたばたしてました。
少しは綺麗にしないと思い、片付け開始。
なのですが、なぜか昔買ったが読みかけの本を発見。
ビジネス本はIT関係でなければ、少々古くても役に立つ。
「エスキモーに氷を売る」
「なぜ、あの商品は急に売れ出したか」
は何度読み返しても、刺激を受けます。
当然、片付けは進みません。
なぜこんな本をとっておいたか?
「ひとり暮らし 料理の技術」
津村 喬 著
1977年の本ですから、約31年前購入です。
まだうら若き、IVYBOYでした。(笑い)
この中に、料理道具に関する記載があります。
当時はまだコンピューター会社でSE修行中でしたから
まさか、包丁製造販売の仕事をするとは、考えてもみませんですね。
その包丁に関する記載を読んで、おもわずにんまり。
料理の半分は切ることにある。
とりあえず買いたいものは、万能包丁、砥石とありました。
包丁だけは良いものを買いたい。
切れない包丁は材料を切らずに、つぶすことになる。
等と記載されてました。
良いこと書くね、一人よがりです。
そんな訳で、徳蔵のペテイナイフ。

最近は小ぶりの食材が多いので、多分、最初はこれ一本でOKかも。
ダマスカス鋼で錆びにくい。(錆びないと書きたいくらい)
それに柄もしっかり出来てます。

マホガニー合板で、いかしてます。
★メールでのお問い合わせは★
お気軽にこちらへ
★電話でのお問い合わせ★
TEL(048)431-6600
★徳蔵ウエブは★
製品情報満載
Posted by 輝 at
16:02
│Comments(1)
2008年08月18日
お宝探検隊
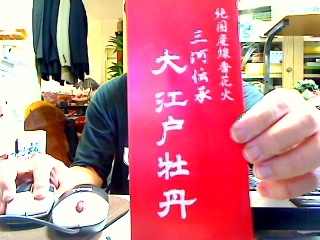
昨年同様に、線香花火の手配を頼まれました。
幸いな事に完売で、手元にはこれしか残っていません。
秋の気配が漂う夜にでも、楽しもうかな。
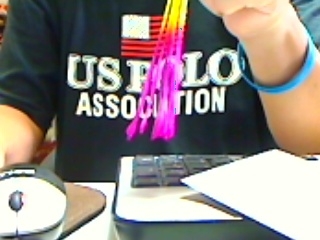
この花火は選定条件が厳しくて、国産(日本国産ですぜ)、
手捻り、花が大きい事などなどです。
探すのに一苦労。
そんなときに手を貸してくれた、蔵前の花火屋さん。
人のご縁は大切にですね。
お取引が出来て、お支払いもしっかりすれば、ご縁は長く続きます。
花火手配を頼まれたバーヤーから今度はおもちゃで何かないか?
子供の?大人の?とチビット際どい質問ですが、当たり前、大人も子供も
喜ぶものだと言われました。
前出の蔵前のだんなさんが、輝どん、うちの倉庫を開けるから、良かったら
おいでよとのお言葉。
渡りに舟、地獄で仏、たあこのことだ、勇んで出かけました。
草ぼうぼうの中で、倉庫係りの方が、草刈の真っ最中。
早速、探偵団団長よろしく、ご入場。
おどろいたねえ。
確かにブームの頃に、その筋の(怪しい筋ではないです)方々が、札束に物を言わせて
買いあさったそうです。
ブリキのおもちゃです。
そんなに絶品(評価価格が高いと言う意味です)はないですが、まだまだありました。
詳しくないのですが、名前だけは知ってるあの、イチコーさんのブリキおもちゃ。
これらは復刻版です。
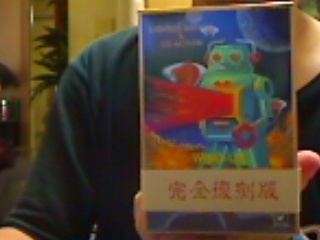
今は廃業されたそうですが、当時のにおいはしますね。

まだまだありましたが、蚊の大群に襲われて。退却です。
入り口で見つけた、地球ゴマ、懐かしいな。
でも昔のものの方が手作り感がありましたね。
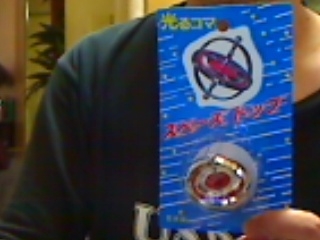
久々に興奮した探検隊でしたが、帰りに駅前で買ったキンカンを塗ってまた塗って大笑いの巻きでした。
また行きたいな、札束持ってさ。
Posted by 輝 at
08:41
│Comments(1)
2008年08月16日
上手い鰻でした

お盆で人の数も少ないですね。
たまには贅沢?をと出かけた先は、蕨の鰻や「みさ和」さん。
美味しいとは評判ですが、はじめて行きました。
引退した力士、闘牙関の半浴衣を着込み、下駄で出かけました。
まずはビール。
付き出しは店頭で売られている、昆布の佃煮。
これが美味。
肝焼きも頼んだのですが、これを一口いただいた時に
この店は自分に合うと思いました。
肝の焼き加減、たれの美味しさ、抜群です。
お酒を少しいただいて、特上(生意気)を注文しました。
当然ですが、大満足。
帰りには店頭で佃煮をお土産に静かにご帰宅。
蕨にも美味しいと評判のお店は数多くあります。
鰻は美味しい事はもちろん重要ですが、自分に合う
味(たれ、焼き加減)で贔屓が決まります。
我の母の実家が静岡県三島市の老舗の鰻やでした。
屋号は「宮勝」。
残念ながら店はすでに廃業しました。
高校生の頃は出前でアルバイトしました。
乗り物酔いのスゴイ母でしたが、一度だけ東京に来ました。
東十条の知り合いのお店「川辰」さんで鰻を食べましたが
実家「宮勝」の味と同じだと言った事が思い出されました。
その「川辰」にも勝るとも劣らない「みさ和」さん。
これからも行きたいです。
そうそう鰻の好きな番頭さんにも食べさせてあげたいですね。
Posted by 輝 at
11:29
│Comments(1)
2008年08月14日
夏祭り前夜

祭りの前はわくわくします。
我が故郷、静岡県三島市大社神社の夏祭り。
ここ数年は9月の母の墓参りがあるので、行く機会も少なくなりました。
伊豆一ノ宮とも言われ、源頼朝ゆかりの神社です。
8月15日から三日間、市内はお祭り一色。
子供の頃は祖母の隠居には、修善寺、東京などなどから、孫が一斉に集合。
出面勘定は我の役目で、人数によりサイダーの買出し、スイカの川冷やしの準備などする訳です。
夜は祖母につかまりながら、ヨーヨー、海ほうずき、地球ゴマなんかを買って貰います。
今は昔ほどではないのですが、ここは山車(喧嘩山車)で有名でした。
大社神社の鳥居前に各町会の山車が集まり、シャギリで競い合います。
子供の頃は、この後を追いかけて、迷子になること、数知れずでした。
気が付いたら、違う町会の山車を引いていました。
そのご縁?で高校時代はこの山車の飾りを担当していました。
叔父が太鼓の名手でよく教えてもらいましたが、私はシャギリの方が好きで
得意でした。
懐かしいな、シャギリはチャンチャンチャンチャンチキチの繰り返し、
太鼓はちゃらおかし、ちゃらおかし、あの子のしゃっらまだおかし、
と覚えます。
今では従兄弟が後を継いで、頑張ってます。
昔はこの境内で仕掛け花火をやったのですから、すごい事でしたね。
今は危険だと中止になりましたが。
境内の奥には鹿がたくさん飼われていました。

少し離れたところですが、「御神馬」も祭られています。

宝物殿には刀剣類も多く飾られ見ごたえ満点。
近くには佐野美術館もあるので、刀剣ファンには良いところです。
祭りの前はわくわくですが、祭りの後の片付け作業は寂しいものでした。
でも良いですね。
遠くで鳴る花火の音を聞きながら、一杯も。
北原謙二の歌にありますね。
故郷の話をしよう。
君の知らない僕の故郷、故郷の話をしよう。
Posted by 輝 at
16:12
│Comments(1)
2008年08月13日
修理:鯉口の緩み
居合刀は経年使用で、鯉口が緩くなる事があります。
鯉口が甘いなどとも表現します。
鞘口部分、鯉が大きく口を開けた様に見えるのでこの名前が付きました。

今回は鯉口の簡単な修理方法を考えてみました。
準備するものは朴の木の木片があればいちばん良いのですが、
なければ経木などでも結構です。

木工用のボンド・あればピンセットも用意します。
私は関の職人さんからいただいた、厚めの経木(これって割烹料理屋の弁当の蓋?)
を写真の様に、ハサミで切り、紙やすりで薄く削り使います。

貼り付ける前に緩みの程度に合わせ、しっかり削ります。
貼り付けてから棒やすりなどで調整も可能ですが、鞘に傷を付ける可能性があります。
お勧めできません。
以下手順です。
1)刀身を鞘から抜きます。
このときに緩みの程度を確認しておきます。
2)緩みの程度に合わせ、極力薄めに削った木片を準備します。
3)鯉口の刃部分に木片をあてがい、様子を見ます。
万が一厚みを間違えた場合でも、薄めであれば調整が可能です。
そのあたりがコツかも知れません。

4)木片にボンドを薄めに付けて貼り付けます。
このときに、ピンセットなどで押さえつけると良いと思います。

5)完成です。
約一日程度は刀身を納めず、しっかり貼り付いた事を確認後に、薄く刀油(椿油でも十分です)
を塗り、なじませます。

もっとも居合の稽古時には、鍔は指先でしっかり押えておくことを忘れずに、暑いですが
稽古に励みましょう。
丁稚も大森流で汗を流しています。
現在4本目を練習中です。(笑い)
★メールでのお問い合わせ★
お気軽にこちらへ
★電話でのお問い合わせ★
TEL(048)431-6600
★徳蔵ウエブ★
製品情報満載
鯉口が甘いなどとも表現します。
鞘口部分、鯉が大きく口を開けた様に見えるのでこの名前が付きました。

今回は鯉口の簡単な修理方法を考えてみました。
準備するものは朴の木の木片があればいちばん良いのですが、
なければ経木などでも結構です。

木工用のボンド・あればピンセットも用意します。
私は関の職人さんからいただいた、厚めの経木(これって割烹料理屋の弁当の蓋?)
を写真の様に、ハサミで切り、紙やすりで薄く削り使います。

貼り付ける前に緩みの程度に合わせ、しっかり削ります。
貼り付けてから棒やすりなどで調整も可能ですが、鞘に傷を付ける可能性があります。
お勧めできません。
以下手順です。
1)刀身を鞘から抜きます。
このときに緩みの程度を確認しておきます。
2)緩みの程度に合わせ、極力薄めに削った木片を準備します。
3)鯉口の刃部分に木片をあてがい、様子を見ます。
万が一厚みを間違えた場合でも、薄めであれば調整が可能です。
そのあたりがコツかも知れません。

4)木片にボンドを薄めに付けて貼り付けます。
このときに、ピンセットなどで押さえつけると良いと思います。

5)完成です。
約一日程度は刀身を納めず、しっかり貼り付いた事を確認後に、薄く刀油(椿油でも十分です)
を塗り、なじませます。

もっとも居合の稽古時には、鍔は指先でしっかり押えておくことを忘れずに、暑いですが
稽古に励みましょう。
丁稚も大森流で汗を流しています。
現在4本目を練習中です。(笑い)
★メールでのお問い合わせ★
お気軽にこちらへ
★電話でのお問い合わせ★
TEL(048)431-6600
★徳蔵ウエブ★
製品情報満載
Posted by 輝 at
07:15
│Comments(2)
2008年08月12日
うろこから芽?

大宮ソニックのセミナーに参加させていただきました。
久々のソニック。
日ごろお世話になっている、中小企業振興公社のO担当にご挨拶。
輝さん以前は、インターネットアクセス(あくせくと言われた事もありますが)向上委員会の
メンバーでもありました。
その時の仲間でもあります。
お互い様ですが、我々は(正式には我はですが)大宮の駅はこちら側が守備範囲ではあります。

セミナーは「御社のホームページがダメな理由」で著者の竹内謙礼氏の講演です。

実はアマゾンでは結構厳しい書評でしたので、おおいに興味があり、折角のチャンスと出かけた次第です。
結論ですが、目からうろこが数十枚落ち、そのうろこから目(芽)が出てくる予感がしたセミナーでした。
今までにも多くのセミナー、講演に参加させていただきました、実例を前に、見事にコンサルされた竹内氏
ただものではありませんですね。
ブログでは十分書ききれませんが、ブログ仲間のお兄さん、お姉さんには近々、再現してお見せします。
おもろーーーーーい。
Posted by 輝 at
19:24
│Comments(1)
2008年08月11日
八丁堀まで
会議で八丁堀まで出向きました。
どうせ行くなら、銀行まわりもついでにと、東京駅の台湾系銀行へGO。

ニンハオ、シェイシェイ。
丸の内は様変わり。
緑も残してあり、ビルの谷間を吹く風は、結構涼しいです。

少しだけまわりを眺めて

このまま、歩いて八丁堀まで。
東京駅、丸の内側から八重洲側に抜けて、大丸から地下道へ。
ブリヂストンビル近くで地上にひょっこり顔を出します。
あとはまっすぐ、八丁堀まで。
意外と近いけど暑いでした。
どうせ行くなら、銀行まわりもついでにと、東京駅の台湾系銀行へGO。

ニンハオ、シェイシェイ。
丸の内は様変わり。
緑も残してあり、ビルの谷間を吹く風は、結構涼しいです。

少しだけまわりを眺めて

このまま、歩いて八丁堀まで。
東京駅、丸の内側から八重洲側に抜けて、大丸から地下道へ。
ブリヂストンビル近くで地上にひょっこり顔を出します。
あとはまっすぐ、八丁堀まで。
意外と近いけど暑いでした。
Posted by 輝 at
16:42
│Comments(1)
2008年08月08日
蕎上人

そばと入力して変換すると「蕎麦」とでるので、
ついつい蕎麦上人と記載してしまいます。
正しくは「蕎上人」です。
そばしょうにんと読みます。
ご挨拶とご依頼の蕎麦包丁の納品で出向きました。
前回は墨流し仕様の蕎麦包丁をご依頼いただきました。
今回はやすき白紙の包丁です。

ご店主から開口一番、先日のペティナイフが良いので、少し納めて下さい。
暑さも吹っ飛ぶ、ありがたいお言葉。
これがその一本です。
徳蔵作の逸品と自信を持っています。
材質はダマスカス鋼(名前が怪しいですが、品質は怪しくありませんので)
錆びないと言い切りたいくらい、錆びません。
切れ味も折り紙付き。
長切れすると言います。
ご主人は海釣りがご趣味ですので、現場にも持って行くそうです。
お店では、お刺身もこれでチョチョイと捌くそうです。

無事にお納め終了。
速やかに仕事モードからお客モードに変身。
こうしてお返しするのも礼儀といつも心がけてます。(笑い)
まずはエビスビールの生ですね。
それと
蕎麦味噌焼き
板わさ

徳蔵番頭さんもにっこりです。
日本酒に切り替えて、お蕎麦をいただきます。
本当はお蕎麦の前に、そばがきをいただきました。
土佐醤油(削りたて鰹節、刻みのり)がまた上手い。
写真撮る前に無くなっちゃいました、あしからず。
お蕎麦は田舎打ちです。
これが大好きです。

このお店では蕎麦職人を養成する教室も開校しています。
意外ですが、定年してご夫婦二人だけの生活になり、古民家を使い、
蕎麦屋を開業する方や、趣味はもちろんですが、自店のメニューに
蕎麦を加えたいなどの方の入校があるそうです。
詳しくは
★蕎上人様★
http://www.soba-shonin.com/
★蕎麦包丁詳細★
http://tokuzojp.tencho.cc/e20874.html
★メールでのお問い合わせ★
tokuzo@lmc-portal.net
★電話でのお問い合わせ★
TEL(048)431-6600
★徳蔵ウエブ★
http://www.lmc-portal.net/tokuzo/
Posted by 輝 at
19:09
│Comments(3)
2008年08月08日
蕎麦包丁:職人様仕様(白紙)

浅草の老舗蕎麦屋さん(蕎上人様)のご指定品です。
一流職人さんの右腕(たまに左腕もありますが)になっていると思うと、責任感が沸いて来ます。
たゆまぬ努力で、たわまぬ刀身。
刃渡り36cmの優れものです。
ご希望の方がいらっしゃれば、販売しても良いとのお言葉でしたので
ご紹介させていただきます。
注)受注生産ですので、約一ヶ月半ご辛抱いただきます。
商品には一年間の保証が付いています。
当方の瑕疵がある場合には、責任もって対応いたします。
自信の作品です。
一年間に限り、研ぎ代は無料サービス致します。
送料のみご負担ください。
<<仕様>>
刃渡り360mm
材質:ヤスキ白紙
鍛冶師の腕が試される逸品です。
数少ない鍛冶師の作品です。
柄部分:取り外し可能
切れ味まさに、折り紙付き。
希望小売価格:120,000円(税別)
特性ケース付き
柄を取り外す為の木槌が付いています。
柄は三郷在住の宮大工、相馬和彦師の力作です。

刀身に合わせ、柄を作ります。
この刀身に負けない柄を考えていただいております。


★メールでのお問い合わせ★
お気軽にこちらへ
★電話でのお問い合わせ★
TEL(048)431-6600
★徳蔵ウエブ★
製品情報満載
Posted by 輝 at
18:48
│Comments(0)
2008年08月07日
久しぶり、浅草

ご依頼いただいた、蕎麦包丁の検品に、浅草に出向きました。
今回は12丁ですので、しっかり時間をとりました。
目利きの番頭、徳さんの指示で、着々と進めました。
終了後、一杯と行きたいところですが、今日は我慢を決め込んで。
帰りに大好きな観音さん界隈へ出かけました。
私はどちらかと言いますと、こちらが好きで、先にこちらに足が向きます。
浅草神社

もちろん浅草寺さんもお参りします。
この時期は特にインターナショナルでやんすね。

ご同業?の店の刀の数々です。
もっとも当方は無店舗販売ですが。(笑い)

裏路地にも楽しみたくさんありますね。
おっとねずみ小僧じゃねえか。
こちとらもねずみ年、とても他人とは思えねえ。

このところはやっぱ「あんどーなつ」で盛り上がりますね。

天気も崩れてきそうです。
まだ後日の納品もあるので、そそくさと帰宅しました。
Posted by 輝 at
13:19
│Comments(1)
2008年08月03日
徳蔵
居合刀:徳蔵拵え

代表作品として考え作刀しました。
それぞれの金具にも多いに拘りました。
<仕様>
刀身:2.45尺
注)お客様の身長、腕の長さを考慮して2.3尺から承ります。
女性の方はご相談ください。
刃文:乱れ(薄刃仕上げ)
注)刃文はお好みでのたれ、直刃(スグハ)などお選びいただけます。

縁頭:鉄地肥後象嵌桜づくし

目貫:ぼたんの図

目貫:仁王の図

鞘塗:黒蝋ひとどめ付き
注)鞘塗りは石目もお選びいただけます。
柄寸:8.5寸
注)手の大きさに合わせて、8寸から承ります。
柄糸:正絹黒
注)綿、皮もお選びいただけます。

下げ緒:正絹黒

鍔:菊花の図
注)選択肢はあまり多すぎてもお客様が迷うばかりですが、
鍔にはこだわりたいと言うお客様の為に、二種からお選びいただけます。

鍔:葵の図

総重量:1200g
抜身重量:940g
この重さですと、上級者の方もお気に召すと思います。
製造は岐阜県関市
希望小売価格(2.5尺で柄巻皮又は正絹):105,000円(税別)
<<作刀に関する事>>
代表作にと考えて作刀致しました。
目貫の仁王の図、浅草寺の仁王像を思い浮かべて作りました。
<<当社作刀手順>>
1)金具準備
2)刀身荒研ぎ(あらとぎ)(砂型刀身使用)
3)刀身本研ぎ(ほんとぎ)
4)刃文付け
5)刀身化粧研ぎ(けしょうとぎ)
6)鞘製作・鞘塗
7)柄製作・柄巻
8)仕組み・調整(組み立て作業)
9)下げ緒巻き
10)検品
11)出荷
★さらに詳しい製造工程★
製造工程が良く判る
★メールでのお問い合わせ★
お気軽にこちらへ
★電話でのお問い合わせ★
TEL(048)431-6600
★徳蔵ウエブ★
製品情報満載
<<製品保証>>
当社製品には保証書(取り扱い説明含む)をお付け致しております。
<<弊社資格>>
埼玉県公安委員会許可第431020010414号
美術品商登録済

代表作品として考え作刀しました。
それぞれの金具にも多いに拘りました。
<仕様>
刀身:2.45尺
注)お客様の身長、腕の長さを考慮して2.3尺から承ります。
女性の方はご相談ください。
刃文:乱れ(薄刃仕上げ)
注)刃文はお好みでのたれ、直刃(スグハ)などお選びいただけます。

縁頭:鉄地肥後象嵌桜づくし

目貫:ぼたんの図

目貫:仁王の図

鞘塗:黒蝋ひとどめ付き
注)鞘塗りは石目もお選びいただけます。
柄寸:8.5寸
注)手の大きさに合わせて、8寸から承ります。
柄糸:正絹黒
注)綿、皮もお選びいただけます。

下げ緒:正絹黒

鍔:菊花の図
注)選択肢はあまり多すぎてもお客様が迷うばかりですが、
鍔にはこだわりたいと言うお客様の為に、二種からお選びいただけます。

鍔:葵の図

総重量:1200g
抜身重量:940g
この重さですと、上級者の方もお気に召すと思います。
製造は岐阜県関市
希望小売価格(2.5尺で柄巻皮又は正絹):105,000円(税別)
<<作刀に関する事>>
代表作にと考えて作刀致しました。
目貫の仁王の図、浅草寺の仁王像を思い浮かべて作りました。
<<当社作刀手順>>
1)金具準備
2)刀身荒研ぎ(あらとぎ)(砂型刀身使用)
3)刀身本研ぎ(ほんとぎ)
4)刃文付け
5)刀身化粧研ぎ(けしょうとぎ)
6)鞘製作・鞘塗
7)柄製作・柄巻
8)仕組み・調整(組み立て作業)
9)下げ緒巻き
10)検品
11)出荷
★さらに詳しい製造工程★
製造工程が良く判る
★メールでのお問い合わせ★
お気軽にこちらへ
★電話でのお問い合わせ★
TEL(048)431-6600
★徳蔵ウエブ★
製品情報満載
<<製品保証>>
当社製品には保証書(取り扱い説明含む)をお付け致しております。
<<弊社資格>>
埼玉県公安委員会許可第431020010414号
美術品商登録済
Posted by 輝 at
16:10
│Comments(1)